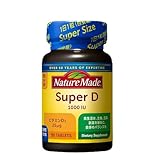「骨密度」の検査、受けてる?数字に目を向けるようになった理由
「骨密度」は多くの人にとってもなじみのある言葉かもしれませんが、私自身も年齢を重ねるなかで、それがより“自分ごと”として実感できるようになってきました。
「これからもずっと、今みたいに元気でいられたら」——そんな気持ちが、自然と“数字”にも目を向けさせてくれたのかもしれません。
毎年の健康診断では、骨密度の検査をオプションでつけるようにしています。(追加料金が安かったのが理由のひとつ)。
今年の結果は、
骨密度(カルシウム量):0.658 g/cm²
YAM値:102.0%(若年成人平均比)
※20〜30代と同程度の骨密度があることを示しています。
「よし、想定内」と思える結果に安心しつつも、数字は“いまの状態”を示しているだけ。
これからも維持できるように、引き続き意識していきたいと思っています。ここに、“まだ大丈夫”という安心感と同時に、“ずっとこのままでいられるとは限らない”という意識も芽生えました。
骨密度のピークはいつ?更年期に減少する理由
骨密度は、10代〜20代前半に増え、20代後半〜30代前半ごろにピークを迎えるとされています。
この「ピーク・ボーン・マス(最大骨量)」は、その後の骨の強さを左右する重要な基礎になります。
その後はゆるやかに減っていき、閉経前後の数年間で最大20%も減少するともいわれています(elcaminohealth.org)。
「骨粗しょう症」とまではいかなくても、年齢とともに「骨量減少(オステオペニア)」の域に入る女性も少なくないそうです。
痩せ型・運動不足・喫煙・過度な飲酒などがある人はリスクが高く、
「なんとなく健康そう」に見えても、実は骨が弱っている可能性もあるのです。
骨を減らさないために。今できる3つの習慣
骨は若いうちに作られた“貯金”が基本ですが、それを守る工夫はいつからでも始められます。
私自身が続けている、そしてこれからも意識していきたいことを3つご紹介します。
1. ビタミンDのサプリを毎日摂取
私は数年前から、毎日ビタミンDのサプリを飲んでいます。
もともとは感染症対策として取り入れたものでしたが、結果的に骨の健康を支える心強い味方にもなってくれています。
(このあたりのビタミンDの効果については、また別の機会に詳しく書きたいと思っています)
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける栄養素。
不足すると、いくらカルシウムをとっても、うまく使えなくなるんですね。
太陽の光を浴びるのは、ずっと大好きな時間のひとつ。
鎌倉で暮らしていた頃は、海沿いを歩きながら日光をたっぷり浴びるのが心身ともにリフレッシュできる時間でした。
今は海のそばではなくなったので、あの“燦々”とした光を感じる機会が減って少しさみしさを感じています。
特に北陸の冬は想像以上に晴れ間が少なく、新居での初めての冬はびっくりしたほど。
そんな環境のなかでも、外をウォーキングして、できるだけ光を取り入れるようにしています。
2. ヨーグルトでカルシウム習慣
特別に“骨のために”と意識していたわけではありませんが、ヨーグルトは毎朝の習慣。
意識していなかったけれど、気づけば自然と骨の健康に役立つ習慣が続いていたことに気づきました。
3. 下半身中心の筋トレ
最近はスポーツジムにも通いはじめました。
きっかけは「体型を整えたい」という気持ちでしたが、
暑い夏でも快適な室内で運動習慣を維持できることに加え、骨や筋肉への良い影響も実感しています。
筋肉の約7割は下半身にあると言われていて、代謝を上げたいなら下半身をしっかり鍛えるのが近道なんだとか。
それを聞いてからは、特に脚やお尻まわりの筋トレを意識して、
スクワットはトレーナーに教わったフォームで自宅でも丁寧に続けています。
骨は、使うことで強くなろうとする性質があるそうです。
見た目の変化だけでなく、内側へのアプローチができる筋トレは、まさに“骨の味方”。
地味だけど、確実な投資みたいなもの。いまはそんな感覚で取り組んでいます。
骨密度という“数字”を、自分の味方に
健診の結果を見るのは、昔からちょっとした楽しみでもあります。
悪い結果は出ないだろうという自信もありつつ、毎年の変化を見比べるのが楽しみになっています。
「去年より減ってないかな?」「この生活で維持できてるかな?」
そんなふうに、自分の体とささやかに向き合う時間になっています。
骨密度は見えないけれど、確かに“自分を支えてくれている”数字。
だからこそ、これから先の自分にも「大丈夫だよ」と言えるように、
今のうちに少しずつ、できることを続けていきたいと思っています。
骨密度は、未来の自分を支える“見えない指標”。
今日の小さな習慣が、これからの10年、そしてその先の安心につながっていく。